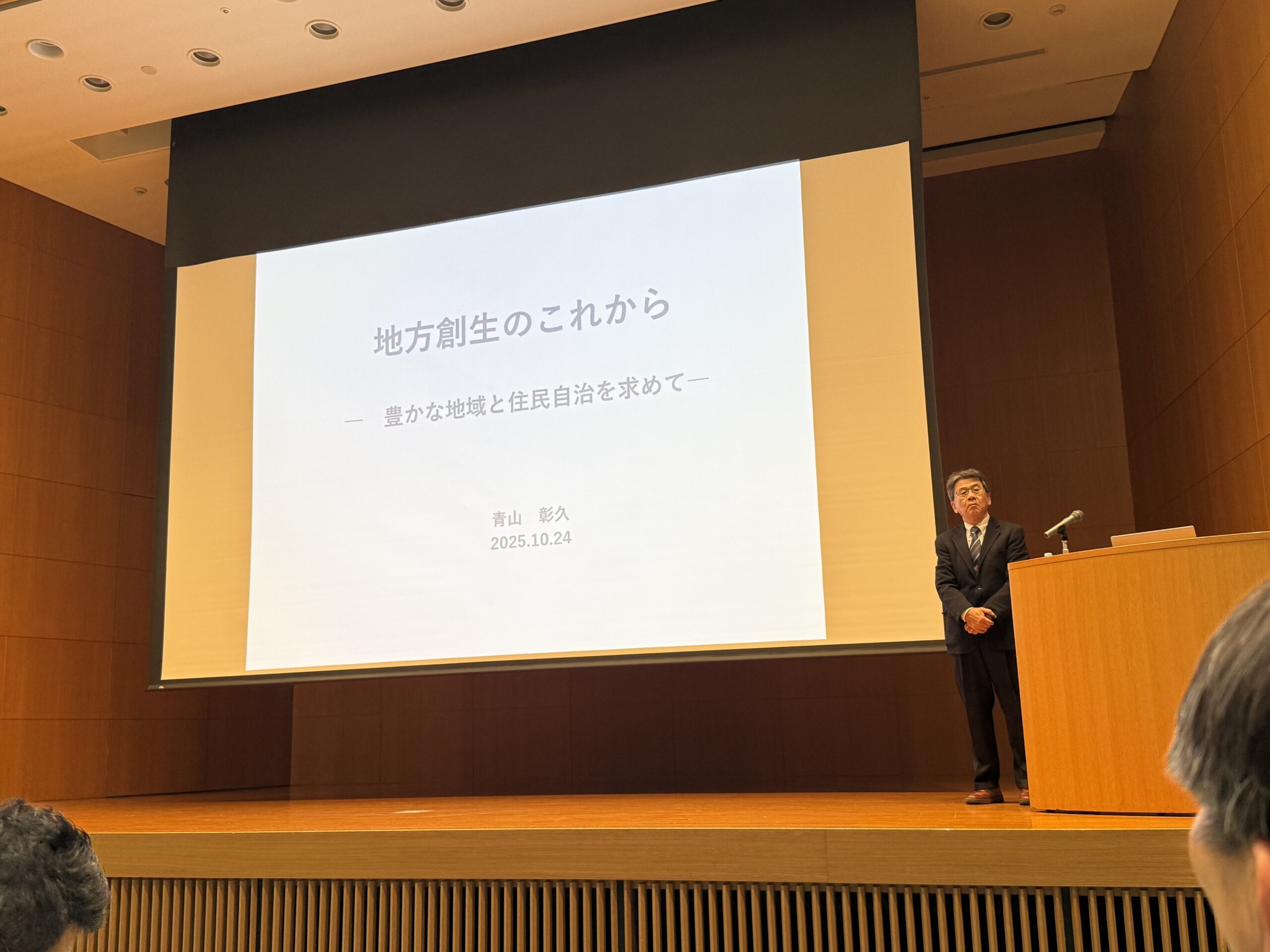地方創生とは、「住めば都」の実現だと思う。
市町議会議員合同研修会で、“地方創生”に関する講義を聞きました。
講師の方は「人口減少への対応」という視点から地方創生を語られていました。
確かに、それも大切な一面だと思います。
けれど私は、少し違う角度から考えています。
地方創生とは、人口を増やすことではなく、「この土地で暮らすことが豊かだ」と感じられる社会を育てること。
私はそう考えています。
経済と人口の関係
経済成長と人口増加は確かに連動します。
重工業中心の時代には、日本も急成長し、人口が爆発的に増えました。
今、世界で経済成長が著しい国も同じ構図です。
人の数=経済成長。
この言葉は、少なくとも“工業の時代”には正しかったと思います。
けれども、経済が成熟すれば、人口の伸びは止まります。
そして今の日本でも、成長が見込まれる産業のある地域――たとえば熊本県菊陽町のように――では人口が増えています。
つまり、産業が生まれれば人口は自然と増える。
これは変わらない原則です。
地方が疲弊している本当の理由
答えは明快で、成長の種をどう育てるかにかかっています。
だからこそ、企業誘致や産業の育成に各自治体が懸命なのです。
経済が動けば人が動く。
それを促すことが“地方創生”の一つの側面だと思います。
あわら市の可能性
あわら市は、昼間人口が夜間人口を上回る町です。
就従率1を超える自治体は、福井県内でも鯖江市とあわら市だけ。
つまり、「働く場所」はある。
それでも若者が帰ってこない。
「希望する職場がない」とよく言われますが、
その“希望”とは何でしょうか。
いわゆるホワイトカラー?有名企業?
それは言い訳に過ぎないかもしれません。
これからAIが社会を変える第4次産業革命の時代、
多くのホワイトカラー職が消えるとも言われています。
そうなったとき、働く場所は“どこでもいい”という時代が来る。
むしろ地方こそ、新しい働き方の舞台になるかもしれません。
地方創生の本質
では、私が考える“本当の地方創生”とは何か。
それは「住めば都」の実現です。
どこに住んでも、文化的で安心できる暮らしがあること。
その環境を整えるのが行政の役割だと思います。
行政は究極のサービス業です。
道路を整備し、支援策を用意することも大事ですが、
“あぜ道はあぜ道のままでいい”という感性も、同じくらい大切です。
そこにしかない美しさや、暮らしの形があります。
その価値を守り、磨くことが地方創生の核心だと思います。
東京もまた「地方」
私は、東京もまた“地方”だと思っています。
東京にないものはここにある。
ここにないものは東京にある。
それでいいのです。
日本中に、それぞれの“都”がある。
それが本当の地方のかたちです。
自治の原点
憲法上、中央も地方も対等です。
主従関係ではありません。
しかし現実は、陳情に頼る構図が続いています。
地方は本気で頑張っています。
「消滅可能性団体」と言われても、
それでも私たちはこのまちを守り、ここに暮らす人たちを守らなければならない。
がんばって何とかなるものではない。
それでも、なんとかしたい。未来を見ながら、なんとかしたい。
それが、私の“地方創生”です。
理想と現実のあいだで
私の書いたことは、理想なのかもしれません。
だけど、理想を思い描かなければ、数値目標も何も生まれてきません。
理想を掲げられる人ほど、数字にこだわり、
誰もが「無理だ」と言うことを打破していく力を持っています。
政治の世界だけでなく、ビジネスでも同じです。
理想があるからこそ、地道にできることを、
誰もが嫌がることを、コツコツと積み上げていける。
それが現実を変える力だと思います。
理想を形にするために
私が思う地方創生の第一歩は、“できることを続ける仕組み”をつくることです。
たとえば、地域で働く若者が誇りを持てる環境づくり、
地元企業が挑戦し続けられる制度設計、
そして、地域の声を行政にきちんと届ける仕組み。
こうした小さな積み重ねが、やがて理想を形にしていくのだと思います。
あわら市の専門家として
私は地方創生の専門家ではありません。
しかし、あわら市の専門家として、
このまちに暮らす人の幸せのために行動できる専門家でありたいと思います。
理想と現実のあいだで、私たちは迷うこともあります。
それでも、同じまちに生きる仲間として、共にこの場所を守り、次の世代へつなげていきたい。
その想いを胸に、私は今日もあわらの現場に立っています。